どうも、死ぬときはせめて服を着ていたいダルです。
歴史上の偉人たちには、漫画や映画のようなカッコいい死に方をした人もいれば、悲しい悲惨な死を迎えた人など様々な死に様があります。またその死因も病死・戦死・自殺など多種多様です。
ドラマチックで後世の我々が憧れるような死に方をした偉人もいれば、反対に「え、なんで?」って最期を迎えた人もいます。
 ダル
ダルあなたはどんな最期を迎えたいですか?私は痛みなくスゥーと消えたいです
この記事では歴史上の偉人の「なんでそんな珍しい死に方をしたの?」という変わった死因を紹介します。
大鷲のうっかりが生んだ悲劇アイスキュロス


紀元前455年のアテナイの悲劇詩人アイスキュロスの死因は大鷲のうっかりでした。
アイスキュロスは大鷲にリクガメを落とされて、その衝撃で亡くなったのです。



アイスキュロスの禿げ頭を岩と勘違いした大鷲のうっかりが生んだ悲劇です
またアイスキュロスは「落下物によって死ぬ」という予言を恐れ、屋外で過ごしていたのだとか。まさか紀元前の世の中で、外にいて落下物が降ってくるとは思わなかったでしょう。
リクガメの種類にもよりますが、5kg~数十kgはあったかもしれません。ワシは山羊を運べる種類もいるので、その程度の重さなら難なく運べるでしょう。
あなたも外出の際は、上空のワシに注意してください。
不老不死を追い求め寿命を縮めた始皇帝


初めて中国大陸を統一したことで知られる秦の始皇帝ですが、その死因は自ら飲んだ薬による水銀中毒だとする伝説があります。
始皇帝は不老不死を追い求めた権力者の一人で、徐福という方士(仙術を操る者)に命じて不老不死の薬を探しに行かせるなど苦心していました。
そんな始皇帝が行きついた不老不死の術が「水銀」を飲むこと。
硫化水銀(辰砂)は錬金術や錬丹術で賢者の石と呼ばれるほど重要視されており、これに不死性を見出した始皇帝は、不老不死の薬として服薬したのでした。
ですが実際には水銀は猛毒。脳や神経に重大なダメージを加え、やがては死に至ります。



荒川弘著「鋼の錬金術師」で学んだように、賢者の石は手を出してはいけないのです
戦国ボンバーマン松永弾正久秀
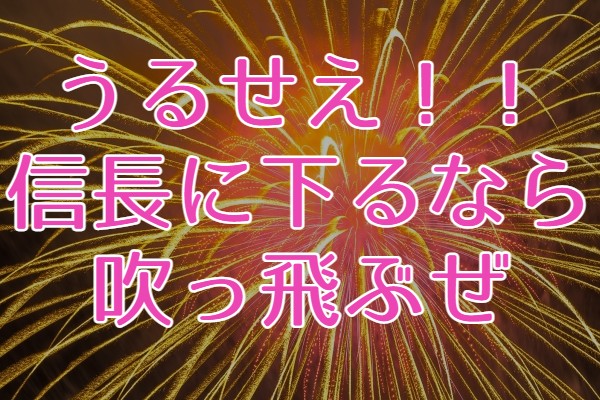
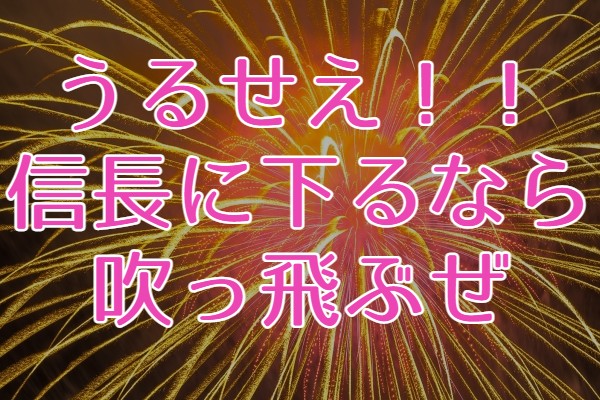
茶釜に火薬を詰めて、自身の城もろとも爆死したという伝説があります。
松永久秀は戦国時代の武将。三好家に仕えた後に織田信長に仕え、奈良の大仏を焼き討ちしたことで知られます。
最期は織田信長に二度目の反旗を翻した際に、信長軍に包囲される中、名茶器である「平蜘蛛」を渡せば助命すると勧告されました。
- 信長:ほら、完全に包囲されてるし出といで。二度目やっけ?かまへんから、平蜘蛛渡してくれたら手打ちにするからさあ
- 松永:…ぅるせ
- 信長:なんてー?とりあえずさあ、出てきてよ。ほら、見て俺めっちゃ笑てるから!一旦帰って敦盛しよ?
- 松永:うるせえ!平蜘蛛も俺の顔も信長にはもう見せねえここでぶっ壊す!チュドーン
このような感じでは全くもってないと思いますが、平蜘蛛に大量の火薬を詰めて華々しく爆死した…というド派手な伝説があります。



実際には自刃したという説が現実的で、現在の主流な説ではありますが、インパクト抜群な説です
信長に対し二度も謀反を起こしていながら、なお助命を申し出されたあたり、相当有能で失うには惜しい人物であったことが伺えますね。
織田信長は第六天魔王のイメージとは違い、意外と筆まめで優しい上司だったと思われます。
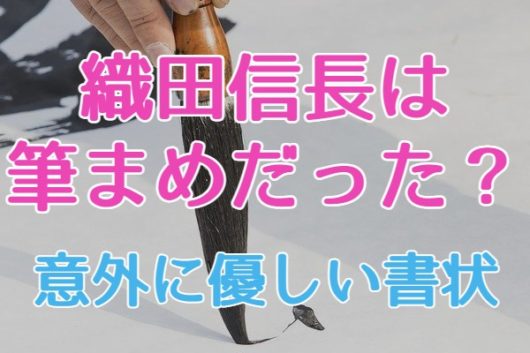
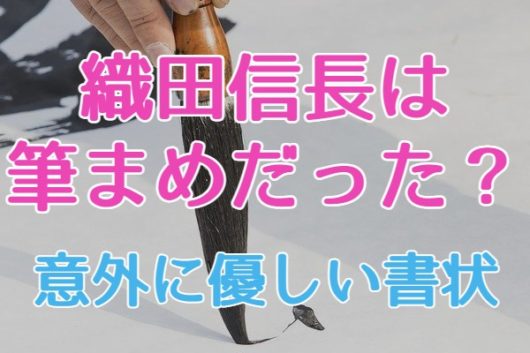
農民の落ち武者狩りに合った明智光秀


明智光秀と言えば本能寺の変で信長を討ったことで有名。大河ドラマ「麒麟がくる」では主人公となっていますね。
歴史に明るくない人でも知っている有名人ですが、その最期はあまりに可哀想なもの。農民たちの落ち武者狩りにあい死亡しました。
本能寺の変後の明智光秀は、毛利攻めを止めすぐさま近畿にかけつけた豊臣秀吉と「山崎の戦い」で雌雄を決します。



結果は豊臣軍の勝利で、明智光秀は敗走します
深夜に少数の家臣らと共に、明智家の本拠であり妻子がいた近江の坂本城を目指した明智光秀。
しかし山科小栗栖にさしかかった際に、突然竹薮から突き出された竹槍に刺されます。



藪からスティックとはまさにこのこと。明智光秀は重傷を負いました
これまでと悟った光秀は、その場で自刃して果てたとされています。当時は普通の村人でも、落ち武者狩りに出ることは珍しくありませんでした。
光秀の最期については諸説ありますが、もしあの信長を討った明智光秀が、農民に討たれて自害していたのであればあまりに悲惨な結末です。
とはいえ戦国時代の農民は現代の我々がイメージするよりパワフルで、戦国武将にも恐れられた側面も。農民の力は侮れません。
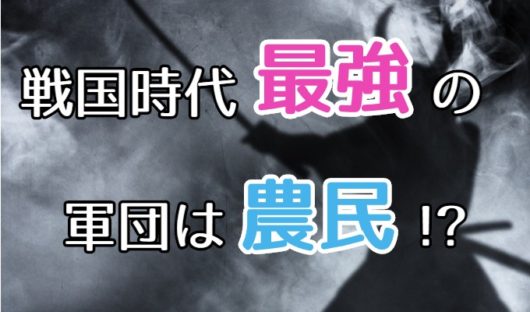
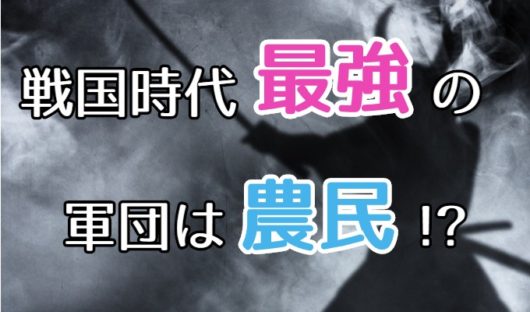
近視で気づいたら敵陣に居たグスタフ=アドルフ


グスタフ=アドルフは17世紀のスウェーデン国王。北方の獅子王ともいわれ、スウェーデンの近代化に貢献した政治家としても軍人としても大変有能な人物です。



スウェーデンを強国としてヨーロッパに知らしめた、まさに英雄的人物です
しかしその最期は、極度の近眼により気づかぬ間に敵陣にいたことでした。
三十年戦争の一幕1632年「リュッツェンの戦い」にて、グスタフ=アドルフは王でありながら自ら全軍の指揮を執っていました。
霧と硝煙が立ち込める中、最前線に立ち続けていましたが、極度の近眼であった彼は気づけば敵陣の真っ只中に。
有能な軍人であったグスタフ=アドルフでしたが、敵陣にまで突出してしまっては太刀打ちできません。



38歳の若さであえなく死亡してしまいます
眼鏡がないと何も見えない私からすれば、他人事ではありません。みなさんも敵軍とは適切な距離を保ちましょう。
歴史上の偉人・英雄だからといって華々しい最期を迎えるとは限らない
華々しく散る英雄や、のんびり余生を過ごす偉人がいる一方で、無念のうちに悲惨な結末を迎えた人たちが歴史上には大勢います。
「人生なにが起こるかわからない」とよく言いますが、こうしたちょっと残念な最期を見るとあながち間違いではなさそうです。
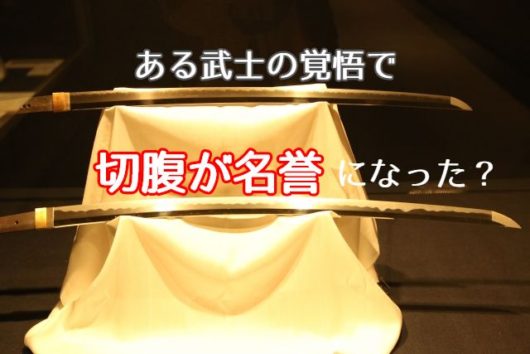
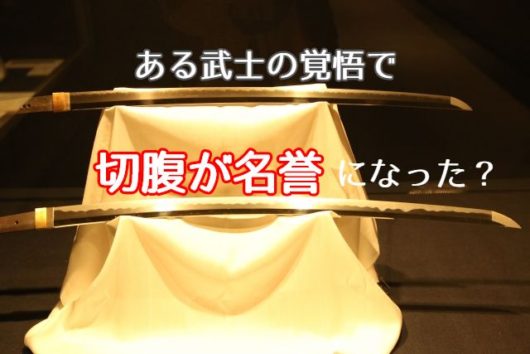
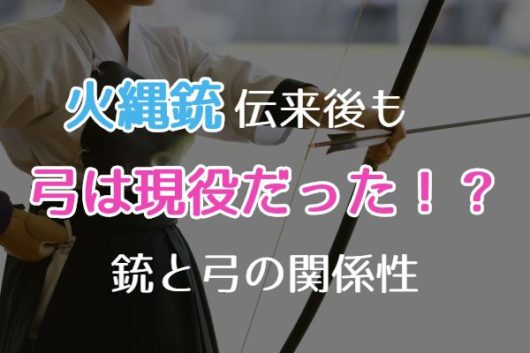
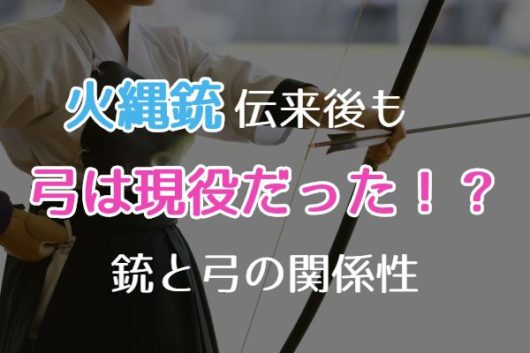

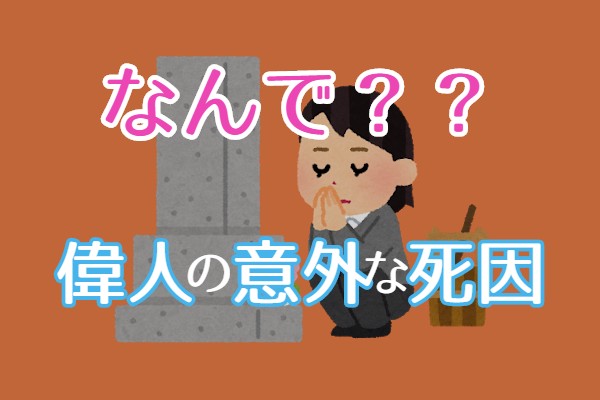

コメント